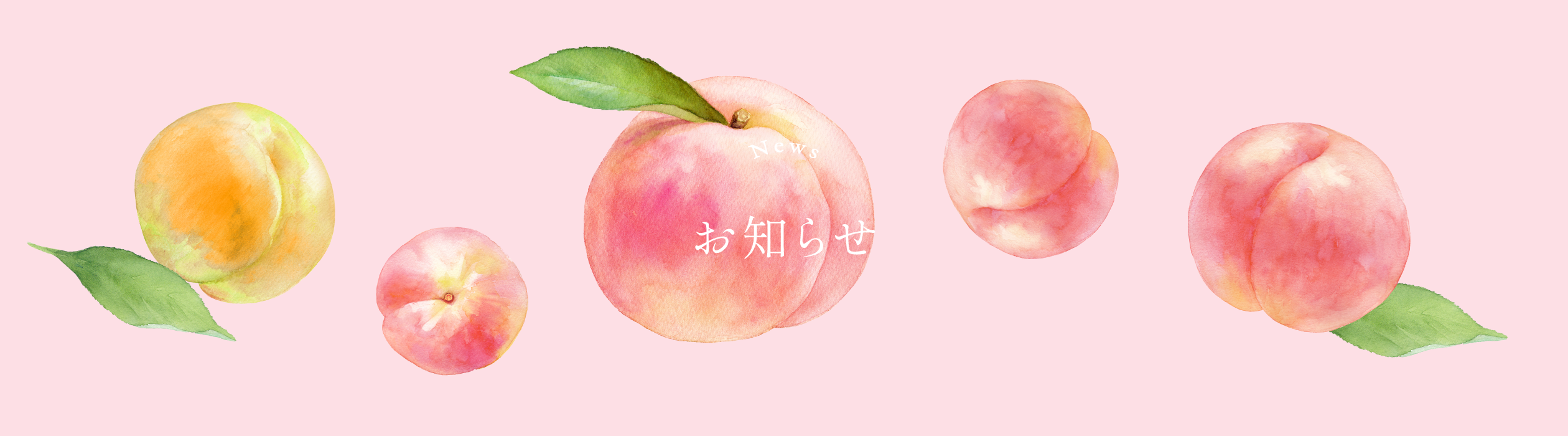
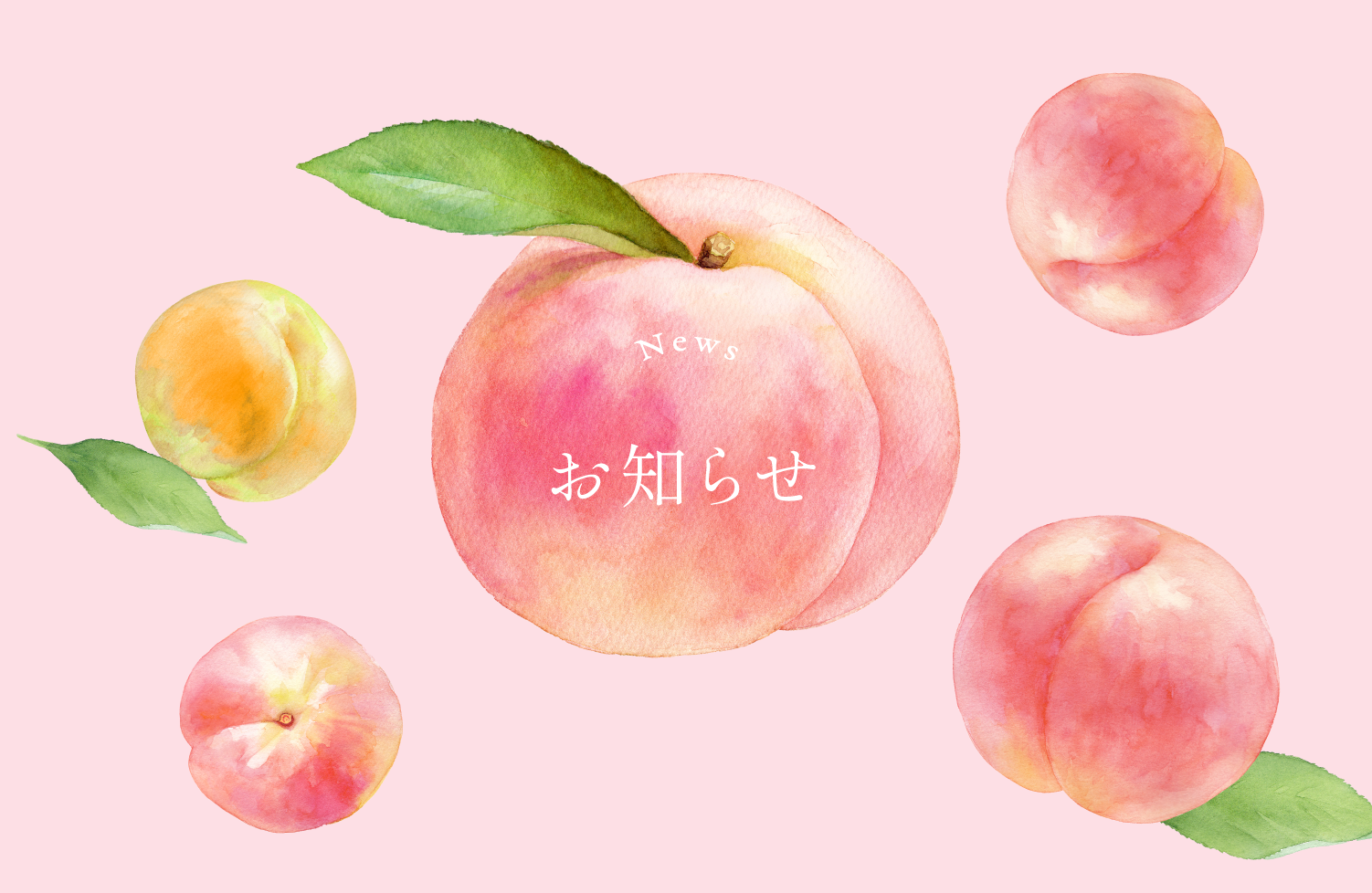
数又組合長:
伊達市の桃は、全国的に見ても品質が高いと評価されています。その理由の一つが、阿武隈川を中心に広がる肥沃な土壌と、桃の栽培に適した気候ですね。もともとは養蚕が盛んな地域だったのですが、転換して桃の一大産地になりました。
福島の桃は、比較的硬めなのが特徴です。また、「無袋栽培」が多く、袋をかけずに太陽の光をたっぷり浴びせることで、糖度が高くなります。特に「あかつき」は、福島を代表する品種で、糖度が安定しており、甘さとジューシーさのバランスが抜群です。伊達市では日本で2番目に光センサーを導入したので、品種ごとの糖度の傾向もはっきり分かるようになりました。

数又組合長:
伊達市で一番多く出回っているのは「あかつき」で、流通している桃の約半分を占めます。ただ、最近は新しい品種も増えてきましたよ。
例えば、「はつひめ」は早生(わせ)の新品種で、出荷が早い時期に楽しめる桃です。早生品種の中では大きめで、甘みがあります。それから、個人的に好きなのは「ゆうぞら」ですね。果肉がとろっとしていて、食べたときの口どけがすごくいいんです。
また、福島で開発してきた「福島18号」「福島19号」も新たに注目されています。ただ、市場に本格的に出回るのは今後10年ほど先になるでしょうか。

数又組合長:
福島県は「日本一の桃の産地」になれると思っています。そのためには、農家さんが農地と技術をしっかり受け継いでいくことが大事です。だから、若手の育成にも力を入れています。
具体的には、経験豊富な農家さんが“先生”になって、2年間の実習を通して技術を伝えていく、いわば「のれん分け事業」のようなもので、新しく桃づくりを始める人でも、しっかりノウハウを学んで地域の生産を支えられるようになります。高齢化が進む中で、こうした仕組みをつくることが、産地を守ることにつながりますね。
ほかには、定期的な木の管理です。木が若いほうが美味しい桃ができるので、計画的に植え替えながら、より美味しい品種を育てていくことが大事ですね。
地域に合った、計画的な園地継承の仕組みづくりをしています。
桃は植えてからすぐに収穫できるものではなく、美味しい実をつけるまでに何年もかかります。今、こうして伊達市が桃の名産地として知られているのも、先人たちが長い時間をかけて土台を築いてくれたおかげです。その先見の明に感謝しながら、私たちも次の世代へとこの産地を引き継いでいきたいですね。

数又組合長:
そうですね。桃は伊達市のシンボルでもあり、地域の活性化にも大きく貢献しています。そのためには、多様な販売ルートを確保することが重要です。
最近では、規格外の桃をジュースに加工したり、スイーツに活用したりして、通年で楽しめる商品開発も進めています。また、家庭の形が多様化する中で、桃の食べ方も時代とともに変化しています。そうしたニーズに対応した販売戦略を考えることが大切ですね。

数又組合長:
やっぱり、高齢化は避けられない課題です。だからこそ、若い世代が農業を続けられる仕組みをしっかり作っていくことが大事。桃畑を計画的に守っていくために、地域全体で支えていく仕組みを強化していきたいですね。
それから、販路拡大の一環として、ヒット商品の開発にも注力したいと考えています。例えば、「桃の恵み」のようなヒット商品を、さらに増やしていきたいです。「桃の恵み」は発売以来、不動の人気を誇る商品ですが、実は、本物の桃100%なので、同じ商品でも年によって味が違うんですよ。そういう伊達市の桃の個性を活かした商品を作ることで、もっと多くの人に伊達市の桃の魅力を知ってもらいたいですね。
数又組合長:
伊達市の桃は、シーズンを通してさまざまな品種があり、長い期間桃が楽しめるのが魅力です。早生の品種から極晩成種まで、リレー形式で味わえる産地って、実はなかなかないんですよ。
ぜひ、旬の時期ごとにいろんな品種を食べ比べて、伊達市の桃の美味しさを実感してみてください!
